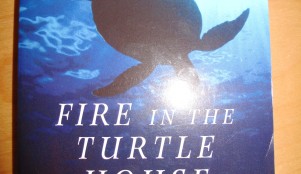ブーゲンビリアは、中央アメリカや南アメリカが原産の低木です。ハワイでは民家の生け垣、ビルのフェンス、ホテルなどにたくさん植えられているほか、レイにも使われ、人気があります。愛好家の間では、「bougies」という愛称でよばれることもあります。 ハワイには今から約200年ほど前に入ってきたと考えられています。ハワイでは主にB. glabrasとB. spectabilisの2種と、多くのハイブリッド種があります。白い小さな花を取り巻く紫、赤、ピンク、オレンジ、白などのたいへん鮮やかな色の葉(包葉)が印象的です。包葉は、原産地に生息するハチドリ(ハミングバード)を誘うために、このような鮮やかな色に進化したのだと言われています。品種によっては、まるでネオンのように鮮やかなピンク色のものもあります。 ブーゲンビリアという名前は、18世紀にB. spectabilisをブラジルのリオデジャネイロで見つけたフランス人航海者、ルイ・アントワーヌ・ド・ブーガンヴィル(Louis Antoine de Bougainville、1729–1811)にちなんで付けられたのだそうです。 日本語名:イカダカズラ ハワイ語名:― 英語名:bougainvillea 学名:Bougainvillea spp. 分類:オシロイバナ科(Nyctaginaceae)イカダカズラ属(Bougainvillea) その他:外来種(alien) ——————————————————————— 「画像1」ブーゲンビリア 「画像2」ブーゲンビリア 「画像3」ブーゲンビリア...
ハワイからのコンテンツ: 全コンテンツ
ブーゲンビリア