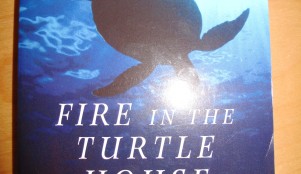シグ・ゼーンといえば、ハワイ島ヒロにある、ハワイアンウェアのお店。オリジナルのデザインが地元の人にも大人気で、私もオアフでシグを着ていると「それ、シグ・ゼーンでしょう?素敵ね。」と必ず声をかけられます。そのシグ・ゼーンがワイキキ水族館とコラボしたデザインを発表しました。Ka Uluwehi O Ke Kaiと名付けられたシリーズは、2011年に亡くなったハワイ大学の海藻学者、ドクター・イザベラ・アボットの誕生日を記念して作られたものです。そこで今回は、ドクター・アボットのお話をさせて頂きたいと思います。 ドクター・アボットはマウイ島ハナ生まれ。彼女はネイティブ・ハワイアンの女性で始めて科学の分野で博士号を取得した人です。さらに、スタンフォード大学の生物科学部において初めて教授職に就いた女性でもあります。世界的にも有名な海藻の分類学者で、100以上もの論文を出版されました。彼女の名前から取って名づけられた海藻の種もあります。晩年はハワイ大学の名誉教授として精力的に活動し、亡くなる数ヶ月前まで、よく大学のオフィスで研究している姿をお見かけしました。 私がドクター・アボットと初めてお話させて頂いたのは、私がオアフではあまり見かけない珍しい海藻を見つけて採ってきた時のこと。大学院生に聞いたところ、彼も見たことが無いので隣のオフィスにいるドクター・アボットに聞いてみたらいいよ、と強く勧められました。当時私はまだ学部生で、有名な海藻学者とお話をするという突然の機会に非常に緊張したのを覚えています。ドクター・アボットは私の取ってきた海藻を見て、その珍しい種類のものに間違いないと教えて下さいました。この時の事は、私の大切な思い出となっています。...