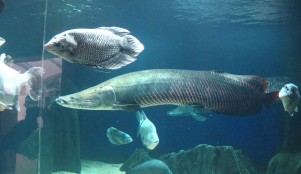エプソン品川アクアスタジアムのナンヨウハギ ちょっと前にカクレクマノミのお話をさせて頂きましたが、カクレクマノミといえばやっぱりニモ。映画「ファインディング・ニモ」には色々な海の生き物が登場しますが、その中でもニモのお父さんと一緒にニモを探す青い魚、ドリーといえば、皆さんすぐにどの魚か思いつくのではないでしょうか?ワイキキ水族館でも、カクレクマノミを「ニモ」と呼んでいる子供達は大抵、この青い魚を見ると「ドリー」と呼んでいます。そこで今回は、この「ドリー」のお話です。 青・黒・黄のきれいな体色 ドリーは日本名でナンヨウハギと呼ばれる魚で、スズキ目ニザダイ科に属しています。サンゴ礁の海に生息していて、体長は成魚で大体20cmくらいです。日本でも暖かい南の海で見られるようです。食べ物は主に動物プランクトンです。特徴はやはりその体の色でしょう。体の大部分はきれいな青色をしていて、体側に黒い線が入っています。尾ひれは黒い縁取りの中が黄色い三角になっていて、熱帯魚らしいきれいな配色です。そのため観賞魚として人気が高く、多くの水族館のサンゴ礁の海の水槽で見る事ができます。 サンシャイン国際水族館のナンヨウハギ 私は水族館に行くとたくさん写真を撮るのですが、このナンヨウハギ、動きが速いのでなかなか上手くカメラに納まってくれません。フムフムヌクヌクアプアアとともに、上手く写真が撮れると非常に嬉しい魚です。...