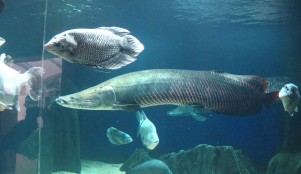ピタヤは、中央アメリカ原産のサボテンです。現在は、花と果実のために世界各地の熱帯地方で広く栽培されています。ハワイには1830年頃にオアフ島に持ち込まれたのが最初とされていて、今日では主要な島々すべてで植えられています。ハワイ在住日本人の間では、ゲッカビジン(月下美人)と呼ばれることがよくありますが、本種とゲッカビジンは別種です。 茎は幅が2~3cmの薄い羽が3つ合わさったような形をしていて、縁は円状に波打っています。壁や木を這うように伸びていきます。花は長さ25~30cm、直径15~25cm。花は夜行性で、夏から秋にかけて数回だけ、夕方に開花して翌朝まで咲いています。果実は赤く楕円形で、長さ5~12.5cm、直径4~9cm。ハワイでは果実をつけることはあまりないようです。 ハワイでは、オバマ大統領の出身校であるプナホウ・スクール(ホノルル市)の、数百メートルにわたる長い垣根に植えられているピタヤが特に有名です。ハワイ語名のpanini-o-Ka-puna-houは、「プナホウ・スクールのサボテン」という意味です。プナホウ・スクールは以前はKa-puna-houと呼ばれていました。 日本語名:ピタヤ(ドラゴンフルーツ) ハワイ語名:panini-o-Ka-puna-hou, papipi pua 英語名:night-blooming cereus 学名:Hylocereus undatus 分類:サボテン科(Cactaceae)ヒロケレウス属(Hylocereus) その他:外来種(alien) ...